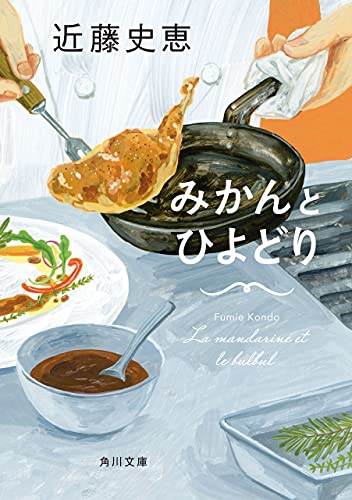神奈川県にお住いの37歳男性(就労移行支援施設通所・クラウドワーカー)が2023年7月頃に読んだ『みかんとひよどり』のレビューをご紹介します。
本書の概要や内容を分かりやすく要約し、まとめておりますので、書籍を読んで学んだことや感想、評価や口コミが気になっている方は参考にしてください。
目次
『みかんとひよどり』を購入したきっかけ
『みかんとひよどり』というタイトルから食べ物に関する本であることは察せられました。
しかし、まさに"みかんとひよどり"という特異な組み合わせが興味を引き、小説そのものよりもレシピへの関心から読むことにしました。
購入の決め手は、小説の表紙に描かれたフランス料理の誘惑的なイメージが料理欲を刺激したことだったと言えます。
購入の動機は食に寄せられたものでしたが、読んでみると小説自体がとても面白く、良い選択だったと思います。
また、全く内容が不明であったにも関わらず、評価が高かったことから面白いはずだと考え、選んだ理由となりました。
『みかんとひよどり』の概要
フランス料理の店の料理人である亮二さんが、猟師との交流を深めながら、食べるという事が何なのかや、店を繁盛させるために必要な工夫について考察していく良書です。
料理を作るだけでなく、猟に出かけたり、人間関係の複雑さや突発する事件など、内容として高い完成度を誇る作品に仕上がっています。
フランス料理について素人でも楽しむことができますし、知識がある方ならば新たな視点から楽しむことができます。
基本情報
- 著者:近藤 史恵
- ISBN:9784041108932
- 出版社:KADOKAWA
- 判型:文庫
- ページ数:304ページ
- 定価:640円(本体)
- 発行年月日:2021年05月
- 発売日:2021年05月20日
- 国際分類コード【Thema(シーマ)】 1:FB
- 国際分類コード【Thema(シーマ)】 2:1FPJ
- 公式パートナーサイト:http://jpo.tameshiyo.me/9784041108932
『みかんとひよどり』のYouTube
『みかんとひよどり』についてYouTubeで解説している動画について調査しました。
しかし、本書を詳しく紹介しているYouTubeチャンネルは見つからず、残念ながら詳しい情報を提供できませんでした。
代わりとなりますが、本ブログでその要点をまとめて伝えたいと思います。
『みかんとひよどり』から学んだことの要約とまとめ
『みかんとひよどり』から学んだポイントは大きく3つあります。
私が学んだこと
- つらいこと=楽しいこと?
- 上手に得て上手に手放す
- 薬喰いで元気に
本文中に、次のような記述があります。
これはこの本の内容を端的に表すものと思います。
「人は野山で一晩過ごしただけで死にそうになるのに、野生動物はその環境で日々生活し、食べ物を探し、敵から身を守っています。
賢くないはずがありません」(本文より引用)。
確かに、人が野山で野宿すると、寒さで低体温症になったり、野生の獣に襲われそうになったり、さまざまな困難が生じます。
しかし、野生動物たちは、そのような困難な環境でも、寒さをしのぎ、外敵から逃れる術を知っています。
その術を知るためには、睡眠中でも敵の存在を察知し、素早く逃げる力が必要です。
これは、我々が感じる安全な環境から大きくかけ離れた、神経を常に高めに保つことを要求しています。
このように考えると、野生動物の生活はきわめて厳しいことです。
また、食物を探すときも、食べ物がある場所を察知する能力が求められます。
多くの人々が見逃すような所にある食物を見つけられるのは、野生動物特有の能力です。
このように、この本では、野生での生活と料理を主要なテーマとし、その中から得た知識によって人間は多くのことを学ぶことが可能です。
つらいこと=楽しいこと?
「フランスにいた時は楽しかった。もちろん、修業は厳しかったし、厨房では差別もあったし、フランス語もなかなか覚えられなかった。つらいことばかりだったはずなのに、過ぎ去った今、あの時が自分の人生で最も楽しかったと感じる」という記述があります(本文より引用)。
つらい経験が楽しい思い出に変わる瞬間があります。
しかし、それがなぜ楽しい感情に変わるのか疑問を抱きます。
私は、これは人間が何かに真剣に取り組むことを本能的に求めているからだと考えます。
つらい経験も真剣に取り組むことで成長の糧となり、困難を乗り越えたときの達成感が得られます。
そして達成感からは楽しい思い出が生まれます。
また、達成感を得られなくても、真剣に取り組むという行為自体が貴重な経験となり、技術的、精神的な成長につながる一方で、楽しい思い出にもなります。
自分自身が真剣に何かに取り組むという経験から、その時間が輝かしい思い出になることを、私はこの本から学びました。
上手に得て上手に手放す
本文中には、「何かを手に入れるためには、何かを手放さなければならない。」という記述があります(本文より引用)。
私自身は人生経験がまだ浅いので、何かを手に入れるために何かを手放すという感覚が理解できません。
しかし、人間関係の繋がりやお金、知識などを得ることで、思わぬ落とし穴が待っていることもあります。
人間関係を得ることで生じるコンフリクト、お金を得ることによる貪欲さ、知識を得ることによる頭に血が上るといった問題などです。
ですから、良いものでも適切に手放す術を知ることは人生をよりよく歩むうえで重要となります。
薬喰いで元気に
本文中には、「僕はジビエで体調が良くなったと感じたことはないが、食べた後、体の末端まで気が通う感覚がある。
江戸時代は、薬喰いと言われたみたいだね」という記述があります(本文より引用)。
ジビエを食べることで全身に血が巡る感覚があるという話ですが、これは元気になることを意味するのでしょうか。
確かに全身に栄養が行き渡ることは健康を保つためには必要不可欠です。
エネルギーレベルの高い食料を摂取することで、体が活性化し、思考も前向きになると考えられます。
そのような効果を「薬喰い」と表現した江戸時代の人々の感覚は、現代でも有効であると思います。
血が巡ることが体調を良くするのであれば、ツボ押しや適度な運動など他の方法でも同様の効果があると思います。
これらすべてが、健康を保つための有効な手段となるのではないでしょうか。
『みかんとひよどり』の感想
命から適切に管理された肉になるまで、数多くの工程が存在します。
私自身を含め、多くの人々はその事実を容易に忘れ、生活しています。
(本文より引用)現代社会で生活している我々は、スーパーでパック包装された肉しか見ることはありません。
しかし、実際にはその肉は鳥獣として生きて動いていた存在であり、生々しい加工の過程を経て食卓に上がっています。
その事実を忘れさせる現代社会の構造には見えない優しさがあると感じますし、それで良いと私は思います。
しかし、時には私たちは、目の前の肉が生きて野山を駆け巡っていた存在を撃ち、ナイフで切り分け、食卓に並べられるまでの過程から命の尊さを学ぶこともできるのではないかと思います。
この本は、その大切さを教えてくれているように感じました。
『みかんとひよどり』の評価や口コミ
他の方が『みかんとひよどり』を読んでどう思われているのか、評価や口コミを調べてみました。
『みかんとひよどり』(角川文庫)そろそろ書店に並んでいると思います。ジビエが得意だけど、店を潰してばかりのシェフと、偏屈な猟師とのバディ未満、みたいな感じの話です。解説は坂木司さん。 pic.twitter.com/z1g3Hab9KM
— 近藤史恵 (@kondofumie) May 25, 2021
✓爆弾
✓同志少女よ敵を撃て
✓鹿の王
✓われら闇より天を見る
✓ハヤブサ消防団
✓ザリガニの鳴くところ
✓熱帯
✓みかんとひよどり
✓舟を編む
✓喜べ、幸いなる魂よ pic.twitter.com/dy8KOIIXXw— m (@dkdkwkwk2828) June 26, 2023
#読了
みかんとひよどり/近藤史恵可愛らしい表題とは裏腹に、ジビエを通し食や生きることについて考えさせられる、なかなか重いテーマの一冊。以前読んだ繁延あづささんの『山と獣と肉と皮』を思い出した。
著者お得意の美味しそうな料理描写はさすがの安定感。ジビエ料理への関心が強まった。 pic.twitter.com/zhTzPN5kYh— まりもっち@読書垢(今年はのんびり読書) (@marimo8989) September 8, 2023
おもしろくて、骨太な面もあり、考えさせられることもいろいろありました。ただ、ビスロト・パ・マルのシリーズのように家で作ってみたいとか、あっ、これ食べたことある!というような料理に関しての共感をそそる部分がやや少なかったのが残念でした。ジビエは好きですが、外でいただくもので家で料理をしようと思わない(する技術がない)ので、ワクワク感がほかの作品に比べて薄いと感じました。時間を置いて読み返してみたいと思います。
Amazonの口コミ
ジビエが小説の素材になることが面白い。小説自体も面白い。解説が坂木司さんなのもわかる。なんか、風合いが似ているような気がする。
Amazonの口コミ
読みやすい文章でサラッと読めます、が、内容は深いです。食べる事とは、生きる事とはどういう事なのかを考えさせます。美味しそうな料理の数々も魅力的です。2011年の原発事故以来近隣の山の物は熊も野草も食べなくなりました。。猪も熊も土地の食べ方で美味しく食べられますが潮野シェフに料理してもらって食べたい!
Amazonの口コミ
久しぶりに近藤さんの本。美味しそうなものが沢山。関西の地名から色々場所を想定。仕事としての料理、趣味としての料理、その中でもジビエの位置。なかなかどうして、オーナーのキャラをはじめ、皆さん特技も個性も豊か。相手を恨みに思って行動する面々のカルト的な側面にうんざりしながらも、理性的に対応する猟師キャラににんまり。さて、ジビエを手頃に食べる贅沢は叶いそうにないけれど、文庫で読むささやかな幸せなら楽勝だ。読後爽やか、この続きはどうなるのか、二人のその後を知りたい。
Amazonの口コミ
ストーリーとして面白かった。人間は、他の生き物の命をいただいているということを思い出させてくれました。
Amazonの口コミ
みなさん本書を読んで学んだことが多いみたいですね!
おわりに
命を等しく見た場合、食物にすらならない害虫はどう扱うべきでしょうか。
ノミやゴキブリを殺すことは残酷だと叫ぶ人は存在するでしょうか。
実験動物のサルやラットに対して同情心を持つのに、飛べなくしたハエの遺伝子解析実験には心が動かされないのはなぜでしょうか。
矛盾はどこまで突き詰めても矛盾のままです。
ですが、我々は考え続けるべきです。
本文から引用します。
確かに、このような問題は多くの課題を含んでいます。
イルカが無慈悲に殺されると守ろうという運動が起こりますが、蚊が無慈悲に殺されても蚊を守ろうという運動は起こりません。
それでもどちらも同じ生命です。
我々は自己都合により生き、数多くの動植物を殺して生きています。
それは仕方がない事象だと私は思いますが、なるべく感謝の念を忘れずに過ごすよう努めています。
例えば、食卓に並ぶ肉は祈りを捧げてから食べ、食事が終われば再度祈りを捧げています。
そして、多くの日本人がこの習慣を持っていると私は思います。
自身のために殺された命に感謝し、食事を摂る。
何気なく唱えられている「いただきます」や「ごちそうさま」の背後に含まれる意味深なメッセージについて考察すると、日本人特有の食文化に対する真摯な姿勢が顕在化するかもしれません。
次に読む予定の本は『裁判官の爆笑お言葉集』です。
「爆笑」という言葉がタイトルに含まれていますが、一覧性を確認すると実際には裁判の公開記録とその評価からなる内容となっています。
その中でも、いじめが原因で事件を起こした被告人に向けて、「私も学生時代にいじめられました。
それでも裁判官にまでなれたのです。
あなたも、罪を償い、自己を律して頑張ってください」という一節が印象的でした。
学生生活は楽しい経験もあれば、いじめに遭遇し苦労することもあり、様々な面があると思います。
しかし、この裁判官はいじめを克服し、社会で成功を収めたのです。
そう考えると、読んでみる価値があると感じ、この本を読もうと思いました。